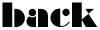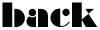第1章 技術論からの審判
1 .<審判員=マーシャルとは何か>
□記録の立証者
審判員は、“選手の成果”を証明する。「正しい記録順位である」と明言できる。例え、第三者から異議がでようとも、自信を持って“説得”できる。これが何よりも重要なことである。
競技の背景を知り、選手の立場を考え、審判員から一方的でない分析があってこそ、自信をもって証明することができる。
しかし、審判といえども人間の判断能力には限界がある。これを補足するために記録を立証できる適切な体制をつくることになる。トライアスロンは、最良の運営があって、審判体制が整うものである。
審判員が対象とするのは、完全に再現することができない“競技者の連続した動き”であり、その動きは競技環境により著しく異なる。
「審判をしやすい環境とは、選手が競技しやすい環境」といえる。しかし、理想を求めすぎるあまり、現実を見落とすことがある。一方で、現実に甘んじるあまり、理想を忘れがちにもなる。
《理想と現実》を直視して、最良の環境をめざす。審判員だけで達成できるものではない。それゆえに、見る立場により価値の違う、多面的な情報に耳を傾けながら、競技記録を立証していくことを目指す。
事例:
JTU猪谷会長が、1954年にイタリアのコルティナダンペッツォの冬季オリンピックのアルペン競技回転で銀メダルを獲得した。このとき、他国のコーチから旗門を正しく通過していないとの抗議があった。しかし、現場の審判員は、「自分の目で確実に見た、私は、ミスター・イガヤの2位を保証できる」と断言した。
「夢と希望に満ちた選手の記録を立証し、保証する審判員」となってほしい。第2種上級審判員面接での、猪谷会長の示唆に富んだコメントである。
2 .<審判員の基本の動きは>
□見届けること。未然に防ぐこと
審判員の対応には、「違反を確実に見届けてから判断する」ことと、「違反を起こしそうな選手に、注意を与える」という二つの方法がある。競技の現場では、両方を使い分けているといえる。
また、失格を出さないよう注意を与えたいが、それができないという場面も多い。このため、ITUの競技規則には下記のように記載されている。
[ Warning : ]
- It is not necessary for an official to give a warning prior to issuing a more serious penalty.
(警告:審判員は、より厳しいペナルティーを宣告する前に、必ずしも警告を出す必要はない)
- The purpose of a warning is to alert a competitor about a possible rule violation and to promote "proactive" attitude on the part of officials.
(警告の目的は、違反が予想される競技者に注意/警告を促すことと、審判員があるべき“自発的な心構え”を奨励することである。)
- A warning will be given at the discretion of the official(※).
(警告は、審判員の判断により発せられる)
「審判員は、ルール違反を未然に防ぐことに務めなさい」ということを強調している。一方で、前述のように、「注意や警告ができないときでも、失格をだせる」ようになっている。
(※)officialは、一般的に、マーシャルとスタッフを含む役員の総称。
事例1:
ドラフティング走行を続けている選手を後走するバイクマーシャルが、規定タイムの15秒を確定するため、念のためストップウォッチで30秒を確認した。そして、レース後、失格を伝えた。
これは、競技規則から正当でありながら、一方で審判員のあるべき対応に不十分さがあった。違反選手に接近し、注意できる位置にいながらそうしないで、「ルール違反を見守った」。“物足りない”と言わざるをえない。
次の機会からは、《競技のガイド役》の気持ちを込めて、口頭であるいはホイッスルを鳴らし、違反状況を教えてやるべきだろう。それでも、距離をあけないときは、ルールに従い、ストップアンドゴー・ルールを適用する。
3 .<競技者の権利とは何か>
□選手と審判。主役は選手
審判員は、選手に指示や注意を与え、警告や失格を宣告する。ときには、教育的指導が必要なこともある。この図式から、選手はあたかも管理の“下”に置かれているようにみえる。
しかし、どのようなときも《主役は選手》である。審判員は、選手を下から支える“支える側の主役”といえる。
選手は、審判員から一方的に指示を受けるばかりではない。ルールから理解できるように、大会の改善要求を行い、意義を申し立て、上訴できる。さらに、上部組織にも意思を伝えることができる。
このように、ルールからも《選手の義務と権利》は一体となっている。正当な方法で権利を駆使するよう、審判員は、これを奨励し、選手の意見を集める努力をする。これにより、選手と審判員・主催者の“適度な緊張感”が生まれ、大会の質的向上の意識が芽生えてくる。
審判員の心得は、「選手が意見を言いやすい雰囲気をつくる」ということである。耳の痛い話しにも、真摯な態度でこれを受け、誠心誠意これに答を出す。
この温和な関係により、大会そして競技団体という組織のなかで、問題を解決する自浄能力を高める。
スポーツをとおした《友好的な人間関係》をつくりあげていきたい。
事例1:
ITUでは、大会から起こる問題解決の手段を明確にし、各国にもこの明文化を求めている。ITU大会では、上訴委員会、ITU理事会、そして総会へとつながり、最終の調停機関を国際スポーツ調停裁判所(CAS)としている。誓約書にも盛り込まれている。
これは、時間的にも経費的にも高額になりがちな民事訴訟を避け、スポーツ競技団体そして所属選手が、お互いの立場を尊重しあい、問題の自主解決をめざそうとすものである。
現在、一般に使用される誓約書では、調停機関を地方裁判所とすることが一般的である。今後は、JTU総会が最終の調停機関であることを、さらに明確にすることが必要になるだろう。
4 .<競技者の責任と運営責任>
□責任の度合いを相殺する
選手がルールを学び、コース環境、交通規則を知ることは義務である。それゆえに、ルール違反は罰せられる。しかし、一方で競技コースに不備があれば、選手のルール順守の意志にかかわらずルール違反は起こりえる。
競技コースの適正参加数を大幅に上回っていれば、集団ができやすく、避けにくい状況が生まれる。
選手は、コースを知る義務を感じていても、これを隅からすみまで知ることはできない。そのため主催者は、注意を促すために看板を出し、スタッフを配置する。
ルール違反はあらゆる要因が複雑に絡み合って起こる。ルールの文面どおりに判定し裁定することはたやすい。
しかし、これらルール違反の要因を考えなければ、「選手に納得いただける裁定」はできない。そのための提案が、それぞれの責任を割合で表し、これらを相殺(オフセット)するという、裁定を緩和する方法である。
事例1:
例えば、競技者の違反に対する責任を100%とする。事前の競技説明の不足が違反を誘発したとする。主催者側に想定される30%の責任を相殺しようとするものだ。
これにより、本来であれば、競技者責任の度合い100%で失格となるものが、70%となり、警告に留まるという考え方である。
これであれば、競技者にも納得してもらえるのではないか。これまでも審判員の頭のなかには、この図式があったろうが、これを数値化し分析していけば、全国の審判員の裁定が均質化する。もちろん双方の向上への努力は必須のものである。
5 .<表現の方法がすべて>
□挨拶と和らぎ
選手に対する、技術・審判員の言葉あるいは文章での表現一つで感情が変わり、そして理解度が大幅に違ってくる。「主催者が作る案内がいかに分かりやすいか、審判員の話し方に思いやりがあり適切であるか」など、多方面に気配りをしたい。
心のなかでは敬意を表していたとしても、それが言葉となって出なければ、相手に伝わらない。主催者そして選手に対しても同様である。「挨拶で始まり、挨拶で終わる」当たり前のことを、審判員みずからが励行したい。
さらに、いかに正しいことを主張していても、その表現が、あまりに一方的で厳しすぎれば、相手は心を開いてはくれないだろう。
大会という緊張度の高い場面では、ことさら「相手に伝える表現力」を高めていかなければならない。一言のやわらいだ言葉が、怒りや興奮を吸収してくれることがある。
事例1:
ボディマーキングを初めて経験する担当者からユニークな報告がある。スタートまで時間があるとはいえ、緊張感が高まっている選手に「おはよう」とまずあいさつし、「この前のレースはよかったネ」と全員に言ってみた。
すると、それまでの緊張感がうそのようになごやかになった。さらに、この担当者は、選手の皮膚の違いにより、マーカーの滑りが全員違うことに気がついた。「選手のコンディションが分かるような気がした」とのこと。何となくいい話だ。
事例2:
「何々をすると失格です」という表現を「こうしてください」と口頭でも文書でも言い換える。これにより、受け取る側の気持ちは変わる。失格という言葉を断定的に使うこともときに必要だが、できるだけ言い換えてみたい。
あるローカルルールで、「スポーツ精神に反すると失格」とある。しかし、ここまで進んできたトライアスロンで、これをここまで強調する必要はないのではないか。また、この精神はJTU規則で網羅されている。
6 .<ものの見方と表現>
□見方により変わる評価
最近の時代を反映してか、「ポジィティブな発想」が強調される。どの角度から物を見るかによって、表現はまったく逆のものとなってしまう。また、その状態も時どきにより変わる。
大会の評価もこれに近いことがある。美しい海に大勢の選手が泳ぎ出すのをスゴイと思う人。一方で、救助が不安と思う人。かくして報告書は、次のような極端に違う二つのものが提出されることがある。
「スイムは水質優良、醍醐味も満点。申し分ない。一斉スタートも交通規制の関係から容認できるものである(容認派の報告)」。
「スイムスタートは、最新の方法に準じていない。いつ事故が起こっても不思議はない(辛口批判の報告)」。
いずれも極端な例であり、まさかこんな報告が提出されることはないだろう。模範となるのは次のような報告である。良いことも改善すべきことも偏ることなく観察していなければできないものだ。
「大会は、伝統的なよさを残しており好感が持てる。スイムは、水質など優良であり、いくつかの点を改善すれば、さらに良い大会になるだろう。検討課題は、ウェーブスタートの導入である。交通規制が厳しいようだが、スタートを15分早めれば、3分おきのスタートができると思われる(包括的な報告)」
いずれにしても、報告の強弱によって、改善すべき一割部分が、ときに九割が悪いようにみえてしまうことがある。
これらに加え、例えば、バイクのアップダウンが厳しければ、危険すぎると感じる人と、技能を試す絶好のコースと感じる人がいる。例題は尽きない。
これとは別に、表面だけを見て、大会を評価することがある。「主催側ではこんな理由があって、こうなっている。その理由も知らないで、あるいは知ろうとしないで、理想ばかりを主張している...」。これは、大会の技術的分析が甘すぎることや、一面的に評価しすぎるために、相手の感情に起伏を起こしてしまうケースである。
大会開催は、経費面、交通事情、さらには週休2日制が一般化し、運営面からもますます厳しい現状に直面している。技術・審判員は、大会主催者を勇気付け、実際に力となる気遣いが必要である。
そのために、「大会の悪いところ」という表現をやめ、「大会の改善点」として統一する。改善点と思うことによって、ネガティブな発想が、すべからくポジィティブに変わる。
良い面を見ようとする気持ちが前に出なくてはいけない。「この方式はダメ」という考えが、「ここをこうしたら良い」となり、主催者の気持ちも前向きになることは間違いない。
事例1:
大会後にアンケートを取り、次年度の改善に役立てていた。初期の頃、いずれの意見も新鮮で真剣に取り組んでいた。しかし、回を重ねるごとに、余りに好き放題な要望が目立ちはじめた。
また、これら要望は、核心を突いたものであっても、その表現があまりに稚拙で第一印象が余りにも悪い。そして、真剣に思い悩むことになる。
一般的にこのような書類は、回覧され上司に上がっていく。「こんな酷い状況は、開催地の名折れだ、何とかするように」。実務者は、このような指示を受ける。
百分の一の意見が、このように辿っていき、担当者のやる気をなくしていく。この解決案は、アンケートを止めることであった。
事例2:
98佐渡世界選手権で主会場のバイクコース上の仮設橋は、「コースを横切らないで観客が移動できる。上位ランナーが遅いバイクと交差しない」など運営面から必須のものであった。
しかし、仮設のため難点もあったろうが、ランコースと観客通路を分けたものは恒久施設としても役立つ高いレベルにある。仮設橋を設置した大会も研究され、経験豊富なスタッフが、数カ月に渡り検討した結果のものである。それでも、もっと良い方法があるかもしれない。
そのため自由に意見を聞き、来期の大会に活用しようとする。これらをすべて理解してもらうには、当初、反対意見の多かった町の中心部を通過する周回コース案の承認に至る作業など、大規模な世界選手権であった。
周回コースについては、世界のトップの限定的競技となったため、これぞ“競技スポーツ”と高く評価された。それでも批判的な意見が出るのは常である。
7 .<選手と審判が一体となるために>
□選手の真剣さに追いつく
従来からトライアスリートは、過酷な条件のなかで挑戦する者というイメージが先行してきた。この精神は大切である。しかし、何がなんでも克服すべきとの考えは、時代遅れとなった。
競技の進展のなかで、選手と審判員の真剣さにレベル差はないか。選手たちの真剣さは、それぞれの動機があり、同一ではないだろう。オリンピックを目指すもの、日常から脱皮しエンジョイする者、体力向上を目指すもの、まちまちである。
審判員は、これらの選手たちの“真剣さ”に呼応し、この気分を盛り上げてやろうという新たな時代のマーシャル感覚を持ちたい。
事例:
競技を行う選手たちが、毎日のように練習し目標をめざしている。その一方で、技術・審判員は、毎日のように研鑽を積んでいるだろうか。大会や審判試験の直前だけ、技術や審判にかかわる社会事象に目を向けても間に合わない。
日頃から、選手の行動パターンそしてその心理面からの動機を知る努力が求められる。「なぜルール違反が起こるのか。なぜマナーが守られないのか」、これを「なぜ交通ルールが守られないのか。なぜ電車のなかでマナーが守れないか」というように比較し、心理を分析してみることが的確なアプローチとなる。
大会でマナーが守れないのは、大会の雰囲気に問題があることが多い。指導する側のマナーを振り返ることも大切な訓練となる。
□ルールの執行者に求められこと
2000年のシドニー・オリンピックの出場資格をかけたワールドカップやITUの承認するワールドポイント・レースが世界各地で展開されている。日本選手もこれらを転戦するようになった。
これにつれ、競技者に課せられるルールも厳しさを増し、広範囲になっている。従来は競技に直結するルールが中心であったが、ユニフォーム・ガイドラインとしてウェアの規制にも及びはじめた。一般国際スポーツと同一レベルになろうとしている。スポンサーロゴの一つひとつがチュックされるようになった。
これを執行するのは審判員である。一方で、審判員には具体的なユニフォームの規制が少ない。しかし、ルールを執行する立場でも、同様のルールが適用されるようになってきた。
選手たちに、「パーティにサンダルはいけない。スポーツマンらしい恰好をするように」と注意する。JTU公式ウェアも揃った。少しづつ改善されている。
暑い季節のスポーツという特性から、堅苦しいものを要求するものではない。しかし、初めて出向く大会に、他大会のTシャツによれよれの短パンでは、良い印象を与えない。大会事務局での態度にも節度が必要である。
何より大切なのは、挨拶である。ハッキリと明るく相手に伝わってこそ挨拶といえる。一般社会での通念である。これらが全うされてこそ、選手たちに注意そして指導する“資格”ができる。
事例:
これについての事例は、残念ながら際限なく枚挙にいとまがない。詳細に報告することは、“発展途上”の名のもとに、ここでは差し控える。
8.<社会的なかかわり>
□社会ルール
トライアスロンや関係する複合競技の大会は、一般競技と同様に、社会的なかかわりのなかで行われるものである。単独では成り立たない。
そのため、特別な許可を受けた競技中であっても、一般社会生活と同様なルールが適用される。
「競技ルールの前に社会ルールがある」。社会人として良識ある言動を心掛けることを強調するのはこのためである。
事例:
最初のウェーブでレースを終えた選手が、観客の多数いるコースわきで声援を送っている。夏の暑いなか、走り続けるレース仲間を応援するいい光景。上半身を裸に気持ち良さそうである..。
そこに、審判員が、「一般の人もたくさんいるのでウェアを着てください」と注意を与えた。“言われたとおりにするか”という感じのなか、そのなかの一人が、「そのようなことはルールに書いてない」という意味のことで反論してきた。
確かにルールにはない。社会ルールに拡大しても、絶対ではない。しかし、プールサイドや海辺でないかぎり、裸でかっぽすることに違和感を感じる人は多いだろう。これを意識できることが社会ルールである。
もし、そのようなことまでルールに明記しなければいけないなら、ルールブックは電話帳の厚さになってしまう。
競技組織との関連
JTUを組織面と競技ルール面で識別すると、組織面では、加盟団体である(財)日本体育協会(JASA)そして準加盟の(財)日本オリンピック委員会(JOC) の指導下にある。そして、99年にはJTUの社団法人化が予定されており、文部省の管轄下に入る。一方、競技運営面では、国際オリンピック委員会(IOC) 、国際競技団体総連合(GAISF) そしてオリンピック夏季大会競技団体連合(AOIF)の正式加盟団体である国際トライアスロン連合 (ITU)を尊重し順守する立場にある。
さらに、ITUでは、関連上部団体として、国際陸上競技連盟(IAAF)、国際自転車競技連盟(UCI) 、国際水泳連盟(FINA)を定義しており、必然的に国内の各競技団体がJTUとの関連団体となる。JTU顧問に各団体の会長に顧問として就任いただいている。
44の国と地域を有するアジアでは、アジアオリンピック評議会(OCA) の承認スポーツとなったトライアスロンを統括するアジアトライアスロン同盟(ASTC)がある。13カ国地域の加盟団体があり、アジア選手権やアジアカップシリーズの開催権を持つ。
2000年のアジア大陸でのシドニー・オリンピック選考試合が、蒲郡で開催される。そして、2002年釜山アジア大会の正式種目になるよう、調整が続けられている。
さて、個々の競技団体に技術委員会 < Technical Committee > があり、加盟組織との連携を強めている。JTU技術委員会そして各ブロックの技術委員会、そしてこれらの根底となる加盟48団体に技術委員会が設立されれば、世界の頂点から日本全国各地へと遠大につらなるトライアスロンの世界的な技術ネットワークが完成する。
JTU公認審判員そして技術関係者の一人ひとりが、世界のトライアスロンを支えているのはいうまでもない。
事例:
ITU設立以前は、世界各地の大会主催者が、実質的な競技団体の役割を果たし、スポーツの発展に貢献してきた。今に至っても、大会主催者の影響力は大きい。
自称“ワールド”問題などで揉めた時期があったが、現在、アイアンマンも含めすべての関係団体組織は、ITUと共同歩調を取りはじめた。
一方、国内においては、大会主催にかかわる競技団体の管轄権が、いまだ確立されたとはいえない。どちらかと言えば競技団体の関与は少なく、個人ベースの活躍に頼るところが多い。
それでも、今後はスポーツ界の相互協力関係によりリスクを分担し、問題解決に一致団結して臨むためにも、大会主催者と競技団体の調和を目指していかねばならない。
9.<大会開催への考え>
□一般規則との関連
交通規制を受けた競技中においても、道路交通法による適用を受けていることは、意外なほど認識されていない。
「交通規制」が、トライアスロンのための「聖域」をつくっていると誤って捉えられることがある。大会は、交通規則を順守しながら、所轄警察に認められた特別なルールの恩恵を受けて開催されていることをぜひ認識したい。
さらに考えなければいけないのは、民事はもとより刑事においても、いくつもの規制を受けながら、大会が開催されているということだ。
事例1:
96年に国際的なスキー大会で重大事故が発生し「安全注意義務を怠った」として、審判長と役員が現地の裁判所に起訴された。国際競技団体側は「事故は予見できなかった」ことを主張した。
最終的には、「道義的な責任」を考慮し、競技団体が5千万円相当の賠償金を支払うことで和解した。トライアスロンでも起こりえることである。
同様のケースが発生したとき、いかに対応するか。そしていかに「有効な事前防止策」が講じられるかが重要な課題となる。
事例2:
路上でゴルフクラブを振っていた男性が、通りがかりの自転車通行人を直撃するとう事故があった。そして、ゴルフ保険が適用されないことに対し、支払い訴訟を起こした。
大阪地方裁判所は、「スポーツには事故がつきものである」と、スポーツに特有の事故を容認する基本見解を示しながら、「スポーツから起こりえる危険を防止せずにこれを行った場合、これはスポーツではなく危険行為である」との見解を示した。そのため保険契約上のゴルフ練習(スポーツの練習)とはいえないと判断した。
この裁定結果をトライアスロンに直接あてはめることはできないだろう。それでも、もう一度“スポーツ”をトライアスロンに置き換えて読み直してほしい。
結論として
これら事例の根底にある考え方は、「危険を承知して参加した“競技者=選手”は、自己の責任と管理のもとに参加する義務がある」とするもので、誓約書にもそのことが冒頭に明記されている。
さらに論を発展させれば、“競技者=トライアスリートとは”どのような定義であるかが問われる場合である。考えられえる答は;
「競技者とは、競技面からいえば、トライアスロンの不安要因を了解し、競技を行える気力と体力そして技術を有する者。また、社会的には、所轄の競技団体に登録している者」
世界の競技団体が、選手からの会費を基本に成り立っている。そして、会員である選手に対し、競技団体は、情報を送り、会員を保護し、権利を守ろうとする。その権利のなかには、役員の投票権が含まれ、トライアスロンを支えるメンバーとしての社会的な認知を得られるということにもつながる。
国際間の大会に参加する場合にも、競技団体同士が、選手の資格そして競技力を保証し、選手に不都合が生じたときは、選手に代わりこれを保護する重要な役割を担っている。
トライアスロンそしてトライアスリートの社会的な立場を確保し、組織的にこの発展を促すことが、起こりえる問題や事故に対応する積極的な方策である。
10.<緊急時への心得>
□事故を想定する
大会関係者は、良い天気に恵まれてほしい、事故なく終了したいなど、大会の成功という一大目標のために、「そうあってほしい」ということばかりを想定しがちである。
当然のことだが、一方で技術・審判関係者は、「起こりえる最悪の事態」を想定して大会に臨まなければいけない。これにより、緊急時の対処方法が、机上の論理でない、現実感を伴ったものとして身に付いてくる。
想定1:
天候悪化でスイム環境が不良となることを予想する。そこで、距離の短縮を想定する。スイム中止を考えれば、デュアスロンへの変更を計画する。ランだけでも汗を流したいという選手の気持ちも考える。
全面中止のときには、パーティだけを開催することも検討される。「好まざる状況を追求する」。これで、綿密な計画ができあがる。
想定2:
バイクコースの途中で事故が起こったと想定する。交通規制のなかでいかに、また何分で現場にたどり着けるか、病院へは発生後、何分で収容できるかを考える。
救急車両が、選手に注意しながら現場に急行する。コースを逆走する箇所があるかもしれない。ブラインドカーブで選手が気がつかないことはないか..、これらを思いめぐらすことにより、「適切なコース設定案」ができあがる。
コース案をつくってから緊急対応を考えるのでなく、緊急対応を第一に考えてコースをつくる。大きな違いである。
これに加え、「緊急車両が通過するときには、周辺に注意し、状況により減速する。必要によっては停止する」ことを要請する。これがルールとなる。
□公的なかかわりと責任
大会は、「所轄機関、住民、ボランティアスタッフ、スポンサー、報道メディア」の五本の大きな柱に、地域競技団体とJTUが連携し開催される。
所轄警察は、地域住民の開催地への賛同を前提に許可を検討する。そのため、例え開催許可が出ても、地域の人たちが迷惑と感じたり興味をなくせば、大会は続きようがない。
とかく所轄警察の許可を大前提に考えがちであるが、「地域を中心とした理解と協力」を第一に考えるものである。普段使っている道路を選手のために開放してくれるものだ。「選手たちが、スポーツの地域振興に協力してやっている」などという考えは通用しない。
そのため、トライアスロン開催の意義を広く伝えるために、地道な準備をしなければいけない。技術審判員の助言が必要な大事な場面である。
具体例:
日本の大会は諸外国と比べ、行き届いていると評価されることが多い。厳しくみれば改善点はあるが全体としては一定の基準が感じられる。各加盟団体の努力にもよるが、行政の横のつながりが、情報を一元化していることも要因の一つである。
さらに特筆できるのは、所轄の警察が大会を管轄し、綿密な指導をしていることである。一般に、外国ではこれほどの協力はない。警察が開催について各条件を出すのは、総合的な管理基準を満たすためであり、「うまくやりなさい」という貴重なアドバイスである。
11.<ルールの背景を知る>
□問題から生まれるルール
ルールが制定された背景を踏まえながら理解することは、単に文面を記憶する以上に有効なことである。
また、その経緯や理由に思いを馳せることは、ほんとうの理由を知らなくてもできる頭の体操である。これはトライアスロンに限定するばかりではない。
「陸上競技のハードルは、なぜできたのだろうか」。ひたすら走ればよいところに、ハードルを置くのに反対がなかったのか。その高さが決まるまでは..」
事例1(ヘルメットのストラップ):
「バイクをラックに掛けてから、ストラップを締めるルール」について。
初期の頃は、特別な規則がなく、降車ラインのずっと手前からストラップを外していた。そして、「トランジションに入るまで外してはいけない」となった。
天草国際大会では、世界的な流れを受け、ローカルルールで数年間の教育期間を設け、数年後にこの規則を正式とした結果、20名近い失格者を出すことになった。ルール徹底の難しさを思い知らされた審判員は多い。
そして、競技力が接近する選手が、さらに集団化するようになり、接触による転倒が目立つようになった。このために、現行のルールができた。
事例2(トランジション):
「トランジション内の乗車禁止」について。
今でも見かけるトランジション内の乗車、あるいはペダル片足走行。投げ散らされたウエットスーツにつまずき転倒、着替え中の選手に接触...。
当然のごとくのルールとなったが、以前のルールに馴染んでいるためか、いまだに、この注意を受ける選手がいる。
事例3(スイム救助の共通サイン):
「スイム緊急時の合図と心得」について。
「競技中に救助を必要とする場合、(競技を停止し)片手を頭の上で振り、声を出して救助を求める」と、統一されている。
“競技を停止して”は、伝えたい意味を明確にするためである。救助を求めるときに、泳ぎながら求めることはない、と考えるものだが、誤解なく等しく理解できる内容に改めなくてはいけない。
ITUでは、"In an emergency, a competitor should raise an arm overhead and call an asistance." と規定している。JTUルールは、これに準拠する。微妙なニュアンスの違いはあるが、選手の動作には違いがでないだろう。
日本文の「頭の上で手を振る」は、raise an arm overhead で、直訳すれば、「頭の上に腕を上げる」となる。助けて欲しいという意思があれば、「振る」という動作がおのずと加わる、という意味が込められている。
いずれにしても、頭の上で手を(ハッキリと)振っているかどうかを救助の現場で問題にするものではなく、ただちに救助に向かうことはいうまでもない。
備考:
以上はほんの一例であり、数えきれないほどの問題を残したドラフティングルールの変遷は多彩である。
ルールは、競技面ばかりでなく社会時世にも影響を受け、問題や疑問そして不安が起こるたびに、検討され改定される。
12.<新たな考え方>
世界の科学の最先端である宇宙開発そして軍事開発においても、人の命を守るために人間は知恵を結集してきた。そこで得られる最新技術や医学が、一般の生活に応用される。
インターネットも元をただせば核攻撃から通信手段を守る技術の応用であった。極限的な場面からの発想そしてトライアルが新たなものを生み出している。
世界で競う選手をスポーツの最先端としたら、“限界に挑んだ結果”から、新たな競技方法が生まれ、同時に問題も起こる。大会を開催する人間は、次々に起こる問題を直視し、解決に当たる。
一般では考えられないわずかな危険防止のために開発の精神が研ぎ澄まされ、ルールが磨かれ還元されてゆく。
最先端であることは、例え一部のものであっても、近い将来には大きな効果を呼び起こす。トライアスロンもこの最先端に位置するようになった。
事例:
人間の“夢”が実現して宇宙時代が到来した。最新の科学技術をトライアスロンに応用する夢を見たい。探査衛星からトライアスリートの動きを逐一フォローする。前方に危険があるとヘルメットに仕組んだマイクロ・レシーバーから警告信号が出る。一方、特殊装置から選手の体内状況が刻々と大会本部の大型コンピューターに伝えられる...。
これは、正に夢の夢かもしれないが、身近な最新技術からの応用も考えられる。ゲームセンターのレースマシンにトライアスロン・コースを再現したらどうか。観客の声援も聞こえてくる。コース状況も伝えられる。そこで、ルールがテレビ画面に映し出される...。
世界の選手を一か所に集めてみたい。そして迫真のレースを見てもらいたい。一人の人間の夢が、人を動かし、歴史に残る世界選手権が日本で開催された。
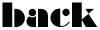
Japan Triathlon Union
Copyright(C)1998 Japan Triathlon Union (JTU) All Rights Reserved.